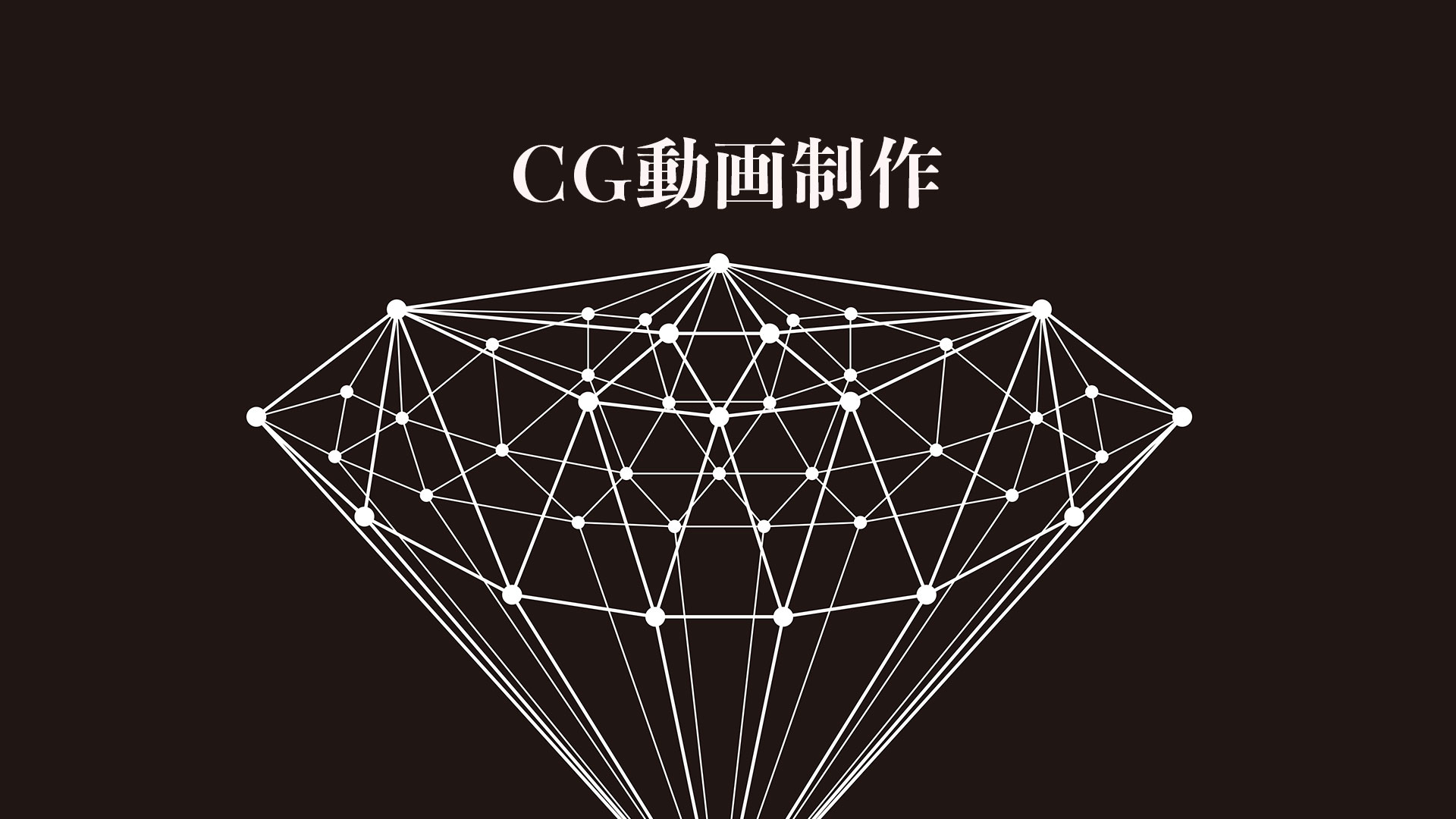コンピューターグラフィックス技術を駆使したCG動画は、実写では表現できない映像や架空の世界観を創造できる強力なツールです。
近年の技術革新により、高品質な映像制作が低コストで実現可能になり、企業PRやプロモーション、教育コンテンツなど幅広い分野で活用されています。
この記事では、CG動画制作のメリット・デメリット、2DCGと3DCGの特徴の違いや、外注と内製のどちらを選択すべきかについて詳しく解説します。
動画制作・映像制作についてお悩みの場合は、お気軽にお問い合わせください。
CG動画とは?
CG動画(Computer Graphics Animation)とは、コンピューターグラフィックス技術を使用して制作された映像コンテンツのことです。
実写撮影では表現が困難な映像や、現実には存在しない世界観を自由に創造できる点が最大の特徴です。
CG動画が注目される理由
近年、CG動画が企業のマーケティングや教育分野で積極的に活用されている背景には、技術の進歩により高品質な映像を低コストで制作可能になったことが挙げられます。
また、実写では不可能な映像表現が実現できるため、視覚的インパクトが強く、視聴者の記憶に残りやすい点も特徴です。
さらに、幅広い業界や用途で活用できる汎用性の高さも、多くの企業から支持される理由となっています。
2DCGと3DCGの違いと特徴
CG動画制作において、2DCGと3DCGの違いを理解することは非常に重要です。
それぞれ異なる特徴と適用場面があるため、目的に応じて使い分ける必要があります。
2DCG(2次元コンピューターグラフィックス)
2DCGは平面的な表現に特化しており、イラスト調で親しみやすい印象を与えることができます。比較的短期間で低予算での制作が可能なため、多くの企業で採用されています。
企業のサービス紹介動画、教育・学習コンテンツ、インフォグラフィック動画、YouTubeのオープニング動画などで効果的に活用されるケースが多いでしょう。
制作コストが抑えられ、修正対応が比較的簡単で、幅広い年齢層に受け入れられやすく、ブランドイメージに合わせやすいという利点があります。
一方で、立体感のある表現が困難で、リアリティのある映像制作には不向きです。また、視点の変更にも制限があるため、複雑な空間表現を求められる場合には適していません。
3DCG(3次元コンピューターグラフィックス)
3DCGは立体的でリアルな表現が可能で、自由な視点からの映像制作ができます。複雑な動きや物理現象も表現できるため、より説得力のある映像を制作することが可能です。
高いリアリティと説得力を持ち、360度あらゆる角度からの表現が可能で、実写では撮影不可能な映像も制作できます。
また、一度作成したデータは再利用性が高いのも長期的なメリットです。
製品の内部構造説明動画、建築・不動産のプレゼンテーション、医療・科学分野の解説動画、ゲームのプロモーション動画などで特にその威力を発揮するでしょう。
ただし、高度な技術と専門知識が必要で、制作時間とコストがかかるほか、ハイスペックな機材が必要となるため、初期投資も大きくなる傾向にあります。
制作期間・コストの比較
一般的に2DCGの制作期間は1〜4週間程度で、制作費用は30〜150万円程度となります。
一方、3DCGの制作期間は4〜12週間程度で、制作費用は100〜500万円程度が相場です。
修正対応については2DCGが比較的容易である一方、3DCGは時間がかかる傾向があるでしょう
CG動画を活用する主なメリット
CG動画を活用する主なメリットは、次の4点です。
存在しないものを視覚化できる
CG動画最大の強みは、実際には存在しないものをリアルに表現できることです。
建設予定のマンションの内装や眺望を事前に確認できたり、新製品の特徴や機能を詳細に紹介したりすることが可能です。これにより、商品のイメージを明確に伝え、顧客の期待感を高めることができます。
さらに、抽象的な概念や複雑な仕組みも、わかりやすい映像として表現できるため、プレゼンテーションや説明資料としても高い効果を発揮します。
商品の魅力を最大限に引き出し、商談や営業活動の成功率を向上させることができるでしょう。
物理法則を超えた表現が可能
CG動画では、物理法則にとらわれない自由な動きを表現できます。製品の内部構造を透明化して動きを見せたり、微細な部分を大きく拡大して機能を説明したりすることが可能です。
例えば、自動車メーカーのCM制作では、エンジン内部の動きや空気の流れを可視化し、製品の性能を視覚的に伝えることができます。また、化粧品の浸透過程や医薬品の働きなど、目には見えない変化も魅力的な映像として表現可能です。
こうした自由な表現力により、商品の特徴や強みを印象的に伝えることができ、視聴者の記憶に残りやすいプロモーション映像を制作できます。
長期的なコスト削減効果
CG動画の活用は、従来の実写撮影と比べて大幅なコスト削減が可能です。撮影場所の確保や出演者の手配、天候や時間帯の制約などにとらわれることなく、効率的な制作を実現できるためです。
また、一度作成したCGデータは再利用が可能で、様々なアングルやバリエーションの映像を追加制作できます。長期的な視点でも、効果的に予算を有効活用できる手法といえます。
柔軟な修正対応
CG動画は、データでの管理が可能なため、修正依頼にも柔軟に対応できます。実写撮影では再撮影が必要な変更でも、CGであれば素早く修正可能です。
例えば実物の商品撮影では、パッケージデザインの変更や色の修正のために再度撮影が必要になりますが、CG動画では、デザインの変更やカラーバリエーションの追加を、既存のデータを活用して効率的に行えます。
CG動画のデメリットと対策
CG動画の主なデメリットと、それぞれの対策も確認しておきましょう。
高額な制作費用
CG動画は、高度な技術と専門的なソフトウェアが必要なため、初期投資や制作費用が高額になる傾向があります。特に3DCGの場合、モデリングやテクスチャ作成に多くの時間と労力が必要です。
また、専門的な知識を持つクリエイターの人件費も必要となるため、予算が膨らみやすい傾向にあります。
しかし、一度作成したCGデータは様々な場面で再利用できるため、長期的な視点で見ると費用対効果の高い投資だといえるでしょう。
企画・設計の重要性
CG動画は自由な表現が可能な分、明確な設計図がないと意図が伝わりにくい作品になってしまいます。
視聴者に何を伝えたいのか、どのような印象を持ってほしいのかという目的が不明確だと、技術的な完成度が高くても効果的な映像にはなりません。
ただし、これは適切な設計さえできれば解決できる問題です。目的とターゲットを明確にし、シナリオを丁寧に作り込むことで、魅力的なCG動画を制作できます。
現実とのギャップリスク
CG動画では理想的な表現が可能なため、実際の商品やサービスとの間にギャップが生じる可能性があります。
完璧な映像表現は魅力的ですが、顧客の期待値が上がりすぎると、実物との差異が問題になることがあるでしょう。
例えば、商品PRでは実物以上の品質や機能を想起させる表現は、クレームのリスクを高めてしまう恐れがあります。
このリスクを回避するには、実物に忠実な表現を心がけ、必要に応じて「イメージです」などの注釈を入れることが重要です。CG動画を制作する際は誠実な表現で、長期的な信頼関係を築きましょう。
CG動画を作る方法
CG動画を作る方法は以下の2つです。
- CGソフトを使って内製する
- 制作会社に外注する
それぞれの方法のメリット・デメリット、注意点について解説します。
CGソフトを使って内製する
CG動画を内製するためには、適切なCGソフトを選ぶことが必要があります。初心者におすすめのソフトとしては、無料で使える「Blender」があります。このソフトはオープンソースでありながら、プロフェッショナルな機能を備えており、2Dと3Dの両方のアニメーション制作が可能です。
CG動画を自作するためには、適切なCGソフトを選ぶことが重要です。初心者には、操作が簡単で基本的な機能が揃っているソフトをおすすめします。例えば、Blenderは無料でありながら多機能で、学習しやすい環境が整っています。初めてのCG制作で予算を抑えたいという方にも最適なソフトと言えるでしょう。
一方、プロフェッショナルな仕上がりを目指す場合には、Adobe After EffectsやAutodesk Mayaのような有料ソフトがおすすめです。これらのソフトは、高度なエフェクトやリアルなアニメーションを作成するための豊富なツールが揃っているため、より複雑でプロフェッショナルな作品を作りたい方に向いています。
CGソフトを選ぶ際には、まず自分の制作目的や予算を明確にし、それに合ったソフトを選ぶことが成功への第一歩です。選んだソフトをしっかりと使いこなすことで、CG動画制作がスムーズに進むでしょう。
制作会社に外注する
CG動画の制作を考えている方にとって、制作会社に依頼することも重要な選択肢です。なぜなら、制作会社には専門的な知識と豊富な経験があり、クオリティの高い作品を短期間で提供できるからです。プロに任せることで、安心して完成度の高いCG動画を手に入れることができます。
制作会社に依頼する際の大きなメリットは、プロジェクト全体を一貫して進められる点です。企画からシナリオ作成、デザイン、アニメーション、編集まで、すべての工程を専門スタッフが担当するため、統一感のある仕上がりが期待でき、予算やスケジュールの管理もスムーズに行えます。
しかし、制作会社に依頼する際には、いくつかの注意点があります。まず、依頼する会社が自分の求めるスタイルや品質を提供できるかどうか、事前にポートフォリオを確認することが重要です。費用についても事前に見積もりを取り、予算内に収まるかを確認しましょう。
CG動画の制作手順
効果的なCG動画を制作するためには、体系的なアプローチが必要です。以下の5つのステップに沿って、詳しく解説していきます。
ステップ1:企画・コンセプト設計
効果的なCG動画制作の第一歩は、しっかりとした企画・コンセプト設計です。
まず、目的を明確化するために、商品PR、サービス紹介、教育コンテンツなど動画の種類を決定し、視聴者に求める行動(購入、問い合わせ、理解など)を具体化します。
次にターゲット分析として、年齢層、性別、職業、興味関心を調査し、視聴環境(PC、スマートフォン、タブレット)や視聴時間を想定しましょう。
さらに競合調査も重要な要素です。同業他社の動画を分析し、成功事例を研究することで、差別化ポイントを明確化できます。この段階で十分な時間をかけることが、後の工程をスムーズに進める鍵となります。
ステップ2:シナリオ・絵コンテ作成
CG動画のシナリオは、映像の設計図となる重要なポイントです。企画段階で決定した目的やターゲットに合わせて、具体的な展開を時系列で組み立てていきます。
基本的な構成として、オープニング(3-5秒)で興味を引き、問題提起(10-15秒)で課題を明確化し、解決策提示(30-45秒)で商品・サービスを紹介し、具体的効果(15-20秒)で利用メリットを示し、クロージング(5-10秒)で行動喚起を行うという流れが効果的です。
絵コンテの作成では、1カットごとの映像イメージを描き、カメラワーク(ズーム、パンなど)を明記し、音声やBGMのタイミングを記載します。これが制作スケジュールの基準となるため、この段階で詳細まで詰めることが重要です。
ステップ3:CG素材制作
承認されたシナリオに基づき、CG素材の制作を開始します。2DCGの場合はイラストやグラフィックの作成から始まり、3DCGの場合はモデリングやテクスチャ作成から進めていきます。
2DCG制作では、Adobe Illustratorでの基本図形作成、色彩設計とブランドカラーの適用、アニメーション用のパーツ分けを行います。その後、After Effectsでの動画編集、キーフレームの設定、イージング(動きの強弱)の調整を実施します。
3DCG制作では、3Dオブジェクトの形状作成、詳細度(ポリゴン数)の最適化、UV展開(テクスチャマッピング)というモデリング作業から始まります。
続いて表面の質感設定、反射率・透明度の調整、物理的特性の再現といったテクスチャ・マテリアル設定を行い、最後に照明の配置と強度調整、影の表現、最終的な映像出力というライティング・レンダリング作業を実施します。
作成した素材は随時確認を取り、イメージとのズレがないかチェックします。
この工程では、特に品質管理が重要です。素材の解像度や形状の精度を入念に精査し、後工程での映像制作がスムーズに進むよう心がけます。
ステップ4:編集・ポストプロダクション
作成したCG素材を組み合わせ、シナリオに沿って動画編集を行います。この段階では、映像の長さ、テンポ、効果音やBGMなど、細かい調整を重ねていきます。
映像編集では、カット編集とつなぎの調整、トランジション効果の追加、カラーグレーディング(色調補正)を行い、音響制作では、BGMの選択・調整、効果音の追加、ナレーション収録・編集を実施します。
最終調整では、全体のテンポ・リズム調整、音量レベルの統一、出力形式の最適化を行いましょう。
例えば、商品PRのCG動画では、最も魅力的なカットを適切なタイミングで配置し、商品の特徴が印象に残るよう編集する必要があります。また、視聴者の集中力が途切れないよう、適度な尺とテンポ感を維持することが重要です。
映像の切り替わりや音声との同期、テロップの表示タイミングなど、細部まで配慮しましょう。
ステップ5:レビュー・完成
最終段階では、企画意図が表現されているか、ターゲットに適した内容か、技術的品質は十分か、音声・映像の同期は正確か、各プラットフォームで正常再生されるかといった項目を総合的にチェックします。
この段階で発見された問題点は迅速に修正し、クライアントの要求品質を満たすまで調整を続けます。完成した動画は、様々なデバイスや再生環境でテストを行い、問題がないことを確認してから納品となります。
CG動画制作のコツ
CG動画制作のコツは以下の4つです。
- メッセージ性の強いストーリー設計
- キャラクターの個性を引き出す
- リアルな動きと表現
- 効果音と音楽の活用
それぞれのコツについて詳しく解説します。
メッセージ性の強いストーリー設計
CG動画制作において、メッセージ性の強いストーリー設計は非常に重要です。
伝えたいメッセージを明確に定義することでストーリーの方向性が決まり、視覚的な要素やキャラクターの行動がメッセージを補完する形で構成することができます。
また、ストーリーの中で視覚的なシンボルやメタファーを効果的に使うと、メッセージがより深く伝わります。
例えば、光と影を使った対比や特定の色を使って感情を表現するなどの手法をすることにより、視聴者は視覚的な要素を通じてメッセージを直感的に理解することが可能です。
最後に、ストーリーの流れをスムーズにし、視聴者を自然に物語の世界に引き込むことも重要です。テンポの良い展開や意外性のある展開を取り入れることで、視聴者は飽きることなく最後まで観続けるでしょう。
キャラクターの個性を引き出す
キャラクターを視聴者にとって魅力的で印象に残る存在にすることで、CG動画の効果を最大限に高めることができます。
キャラクターの個性を引き出すためには、キャラクターのバックストーリーをしっかりと考えることが重要です。
次に、キャラクターのデザインにおいては、外見だけでなく動きや表情にも注意を払いましょう。
例えば、勇敢なキャラクターであれば、堂々とした立ち振る舞いや力強い動きを取り入れると効果的です。逆に、内気なキャラクターであれば、繊細な動きや控えめな表情を意識すると、その個性がより際立ちます。
リアルな動きと表現
リアルな動きと表現をCG動画で実現するためには、物理的な動きを理解し、それを忠実に再現することが重要です。
動きの基礎を理解するために、実際の人間や動物の動きを観察することから始めましょう。例えば、歩く、走る、ジャンプするなどの基本動作を観察し、どのように体が動くかを詳細に分析することが第一歩となります。
次に、キーフレームを使って動きを段階的に設定します。キーフレームとは、アニメーションの始まりと終わりの状態を決めるポイントのことです。
キーフレームを使うことで、滑らかな動きを作り出すことができます。
また、リアルな動きを表現するためには、タイミングとスペーシングを意識することが大切です。タイミングとは動きの速さを指し、スペーシングとは動きの距離を指します。これらを調整することで、より自然な動きを演出できます。
さらに、動きに重みを持たせることも重要です。例えば、物が落ちる際の重力や、キャラクターが走る際の体重移動などを考慮することで、動きにリアリティを加えることができます。
効果音と音楽の活用
効果音と音楽の活用は、CG動画の魅力を大きく引き立てる重要な要素です。
視覚的な要素に音を加えることで、視聴者の感情を動かし、ストーリーに深みを与えることができます。
例えば、アクションシーンでは迫力ある音楽を、感動的なシーンでは静かで美しいメロディを選ぶことで、視聴者の心を揺さぶることができるでしょう。
効果音も音楽と同様に重要です。ドアの開閉音や足音、風の音など、細かな音を加えることで、映像にリアリティを持たせ、視聴者を映像の中に引き込みやすくなります。
音楽と効果音の選定は、動画のテーマや雰囲気に合わせて慎重に行いましょう。
さらに、音のボリュームやタイミングも重要です。映像と音がうまく同期していることで、視聴者は映像に集中しやすくなります。音楽のボリュームが大きすぎると、セリフが聞き取りにくくなることもあるため、バランスを考慮することが大切です。
CG動画制作に必要なもの
CG動画制作に必要なものは以下の3つです。
- ハードウェア
- ソフト・アプリ
- 人材・スキル
制作目的に応じて適切なツールを選択・用意するだけでなく、ツールを使いこなすスキルの習得も必要となります。
ハードウェア
CG動画制作では、以下のようなハードウェアが必要です。
- ハイスペックPC
- CPU(中央処理装置)
- グラフィックボード
- メモリ(RAM)
- 4K以上のモニター
- 外付けHDD
特に、CPU(中央処理装置)は多くの計算を高速で処理するため、IntelのCore i7やAMDのRyzen 7以上のシリーズなど、性能の高いものを選ぶ必要があります。
次に、GPU(グラフィックス処理装置)も重要な要素です。GPUは映像の描画を担当するため、リアルタイムで滑らかな動きを実現するには、NVIDIAのGeForce RTXシリーズやAMDのRadeon RXシリーズなどの高性能なものを選ぶとよいでしょう。
また、メモリ(RAM)も重要です。CG制作では大量のデータを扱うため、最低でも16GB以上のメモリを、可能であれば32GB以上を搭載することで、よりスムーズな作業が可能になります。ストレージについては、SSD(ソリッドステートドライブ)を選ぶことで、データの読み書きが速くなり、作業効率が向上します。
最後に、ディスプレイも考慮に入れるべきです。色の再現性が高く、解像度の高いモニターを選ぶことで、より正確な色調整が可能になります。
ソフト・アプリ
CG動画制作ができるソフト・アプリは以下の通りです。
- 3DCG制作:Maya、3ds Max、Blender
- 2D制作:Photoshop、Illustrator
- 動画編集:After Effects、Premiere Pro
CG動画制作ソフトを選ぶ際は、自分の目的やスキルレベルに応じて最適なものを選ぶことが重要です。
それぞれのソフトには異なる強みや特徴があるため、目的に合わせた機能が利用できるソフトを選択しましょう。
人材・スキル
CG動画制作において最も重要な役割を担うのは、キャラクターや背景を立体的に作成し、動きをつける3Dモデラーやアニメーターです。
次に、ストーリーテリングやシナリオライティングのスキルも必要です。CG動画は視覚的な美しさだけでなく、伝えたいメッセージを効果的に表現することが求められます。魅力的なストーリーを作るためには、シナリオライターの力が欠かせません。
さらに、テクニカルディレクターの役割も重要です。制作全体の技術的な側面を管理し、ソフトウェアやハードウェアの選定、作業フローの最適化を行います。
最後に、効果音や音楽を通じて、動画に命を吹き込む音響デザイナーも忘れてはいけません。音の選び方一つで、動画の印象は大きく変わるため、非常に重要な役割を果たします。
このように、CG動画を成功させるには、多様な専門スキルを持つチームメンバーが必要です。それぞれの専門分野のプロフェッショナルが協力し合うことで、魅力的な作品が生まれます。
おすすめのCG制作ソフト
おすすめのCG制作ソフトは以下の3つです。
- AdobeAfterEffects
- AutodeskMaya
- Blender
それぞれのソフトの特徴について解説します。
AdobeAfterEffects
Adobe After Effectsは、モーショングラフィックスやビジュアルエフェクトの制作に優れた機能を持つソフトウェアです。初心者でも使いやすいインターフェースを備えており、直感的に操作できるため、初心者でも安心して取り組めるでしょう。
このソフトの主な特徴は、豊富なエフェクトとアニメーション機能です。数百種類のエフェクトが用意されており、これを活用することで、プロ並みのクオリティを持つCG動画を作成することが可能です。また、タイムラインベースの編集が可能で、細かい調整や複雑なアニメーションもスムーズに行えます。
さらに、Adobe製品であるため、PhotoshopやIllustratorとの連携がスムーズです。例えば、Photoshopで作成したキャラクターをAfter Effectsに取り込み、動きを付けるといった作業もスムーズに進められます。
一方で、Adobe After Effectsは高機能であるがゆえに、パソコンのスペックが低いと動作が重くなることがあります。このため、使用する際は、ある程度のスペックを持ったパソコンを用意するようにしましょう。
AutodeskMaya
Autodesk Mayaは、3DCGの制作において高度な機能と柔軟性が多くのクリエイターに支持されています。Mayaの強みとして挙げられるのは、その多機能性です。モデリングやアニメーション、レンダリング、シミュレーションなど、CG動画制作に必要な一連のプロセスをひとつのソフトで完結できます。
さらに、スクリプト言語を用いたカスタマイズが可能で、個々のプロジェクトに合わせたワークフローの最適化ができる点も魅力です。効率的な作業が可能となり、クリエイターの創造性を最大限に引き出すことができます。特に、リアルな動きや表現を追求したい場合、Mayaのアニメーション機能は非常に役立つでしょう。
Blender
Blenderは、無料で使えるオープンソースのCG制作ソフトとして、多くのクリエイターに支持されています。「CG動画を作りたいけれどコストを抑えたい」という方にとっては、非常に魅力的な選択肢です。Blenderは2Dアニメーションから3Dモデリング、アニメーション、レンダリング、動画編集まで幅広い機能を持ち、ひとつのソフトで多様な制作が可能です。
Blenderの大きな魅力の一つは、そのコミュニティの活発さです。世界中のユーザーが参加するフォーラムやチュートリアルが豊富にあり、初心者でも学びやすい環境が整っています。
CG動画の制作費用と相場
CG動画の制作費用は、映像の複雑さや品質、制作期間によって大きく変動します。2025年最新の相場情報をご紹介します。
制作費用の内訳
CG動画制作費用は、企画・ディレクション費が全体の15〜20%、CG素材制作費が50〜60%、編集・ポストプロダクションが20〜25%、音響制作費が5〜10%という構成になっています。
工程別の詳細費用は、2DCGの場合は企画・絵コンテが10〜30万円、モデリング・素材制作が20〜80万円、アニメーションが30〜120万円、編集・仕上げが10〜40万円程度です。
3DCGの場合はより高額になり、企画・絵コンテが20-50万円、モデリング・素材制作が50〜200万円、アニメーションが80〜300万円、編集・仕上げが20〜80万円程度となります。
動画の長さ別価格相場
30秒動画の場合、2DCG動画はシンプルなもので30〜80万円、標準品質で80〜150万円、高品質で150〜300万円となります。
3DCG動画はより高額で、シンプルで100〜200万円、標準品質で200〜400万円、高品質で400〜800万円程度です。
60秒動画になると、2DCG動画はシンプルな仕上がりで50〜120万円、標準品質で120〜250万円、高品質で250〜500万円が目安です。3DCG動画は、シンプルな仕上がりで150〜300万円、標準品質で300〜600万円、高品質で600〜1200万円程度となります。
コストに影響する要因
価格を上げる要因は、次の通りです。
- 複雑なキャラクターアニメーション(フルCGキャラクターの制作、リアルな表情や動きの表現、複数キャラクターの同時動作)
- 高度な物理シミュレーション(流体・煙・火の表現、衝突・破壊シーン、髪や布の動きの再現)
- フォトリアリスティック表現(実写レベルの質感再現、複雑なライティング設定、高解像度テクスチャ)
一方、価格を抑える要因は次の通りです。
- テンプレートの活用(既存モデルの使用、シンプルなアニメーション、標準的なエフェクトなど)
- 制作期間に余裕を持つ(急ぎの案件は割増料金、計画的なスケジュール、修正回数の制限など)
予算別にみる制作可能コンテンツ
100万円以下の予算では、2DCGアニメーション(30秒)、シンプルなモーショングラフィックス、既存テンプレートを活用した動画が制作可能です。
100-300万円の予算では、高品質2DCGアニメーション(60秒)、シンプルな3DCG動画(30秒)、複合的な映像表現が可能になります。
300万円以上の予算では、本格的な3DCGアニメーション、オリジナルキャラクター制作、フォトリアリスティックな表現が実現できるでしょう。
CG動画の活用シーンと成功事例
CG動画は様々な業界で活用され、実際に大きな成果を上げています。具体的な活用シーンと成功事例をご紹介します。
製造業・メーカー
製造業では、製品の内部構造説明、機械の動作原理の可視化、安全教育・操作説明、新製品のプロモーションでCG動画が活用されています。
例えば、自動車メーカーA社では、エンジンの燃焼過程を3DCGで可視化した技術説明動画を制作しました。展示会での来場者の理解度が従来の2倍に向上し、商談数が30%増加するという成果を上げました。
効果的なCGポイントとして、透明化による内部構造の表示、スローモーション・早送りでの動作説明、断面図による詳細な構造解説が功を奏しています。
建設・不動産業
建設・不動産業では、建設予定建物のプレゼンテーション、室内インテリアの提案、街づくりの将来ビジョン、安全対策の事前説明にCG動画が効果を発揮しています。
不動産会社B社では、未完成マンションの室内をVRと連動したCG動画で紹介したところ、従来の図面による説明と比べて成約率が25%向上しました。
360度パノラマビュー、時間の経過による光の変化表現、家具配置のシミュレーションといった表現が顧客の購買意欲を高めたといいます。
医療・ヘルスケア
医療分野では、手術手順の説明、薬剤の作用機序説明、患者への治療説明、医療従事者の研修でCG動画が重要な役割を果たしています。
製薬会社C社では、新薬の作用機序をCGで可視化した説明動画を制作しました。医師への理解度調査で95%が「分かりやすい」と回答し、採用医療機関が40%増加という結果を得たとのことです。
分子レベルでの薬剤作用の表現、臓器の内部構造の詳細表示、病状の進行過程の時系列表現が高く評価されています。
教育・研修
教育分野では、学術概念の視覚的説明、歴史的事件の再現、科学実験のシミュレーション、語学学習コンテンツでCG動画が活用されています。
教育機関D社では、複雑な物理現象をCGで解説する動画教材を制作し、学生の理解度テストで平均点が20点向上し、満足度も90%を超えるという成果を達成しました。
CG動画の制作は外注するのがおすすめの理由
上記で紹介したように、CG動画を制作するためには、複数の専門的な知識とツールが必要不可欠となります。
そのため、社内にノウハウやリソースがない場合は、CG動画の制作は外注がおすすめです。
ここでは、外注がおすすめの理由を紹介します。
プロのノウハウを活用できるから
CG動画制作において、専門家のノウハウは作品の質を大きく左右します。
たとえば、商品PRの映像制作では、視聴者の興味を引く最適なアングルや、商品の特徴を効果的に見せるライティング技術が重要です。
これらの専門的なスキルは、独学ですぐに習得できません。
動画制作会社は、クライアントの意図を正確に理解し、目的に合った映像表現を提案できます。
また、最新のCG技術やトレンドを把握しており、時代に即した魅力的な映像制作が可能です。
制作コストを削減できるから
CG動画制作に必要なソフトウェアは、高額なものが多いです。
例えば、業界標準の3DCGソフトウェアであるAutodesk Mayaの通常版の年間ライセンス料は約28.6万円(税込)です。さらに、画像編集用のPhotoshopや動画編集用のPremiere Proを含むAdobeの「Creative Cloudコンプリートプラン」は、年間約93,360円(税込)の利用料がかかります。
さらに、高性能なPCの購入費用やソフトを使いこなすための学習時間も必要です。
一方、動画制作会社に外注すれば、上記のコストは必要ありません。
初期投資や人的コストを抑えたい場合には、動画制作会社への外注を検討することをおすすめします。
<関連記事>
動画制作の費用はいくら?依頼先別・長さ別の価格まで解説【プロ監修】
CG動画制作はAVII IMAGEWORKSへの依頼がおすすめ!
AVII IMAGEWORKSは、神戸、大阪、東京を拠点とする映像制作のプロフェッショナル集団です。
一社完結の制作体制を強みとし、企画から制作、運用までを一貫して提供しています。
実写映像からモーショングラフィックス、CG、VFXまで、幅広い映像表現に対応できる技術力を保有し、ドローン撮影やシネマカメラなどの特殊機材での撮影も可能です。
レベルの高いCG動画を制作したいとご希望の方は、ぜひAVII IMAGEWORKSにご相談ください。
動画制作・映像制作についてお悩みの場合は、お気軽にお問い合わせください。